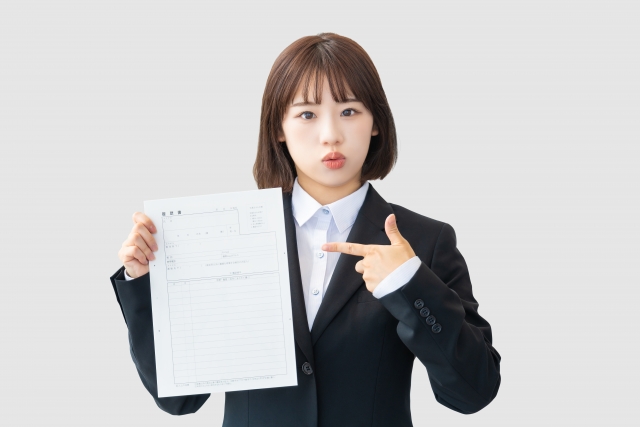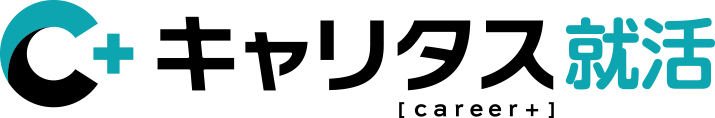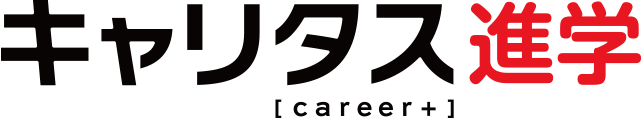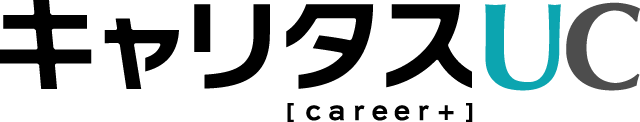初めてでもわかるグループディスカッションの進め方!コツや注意点も解説

初めてグループディスカッションに参加する際、うまく進められるか不安になる方もいるでしょう。グループディスカッションの流れやコツを知っておけば、気持ちに余裕ができて緊張感も和らぎます。この記事では、グループディスカッションの目的、進め方、役割、注意点などを解説します。ぜひ、参考にしてください。
\無料であなたの適性や面接のお悩みをアドバイス!/
会員登録して相談してみる目次
グループディスカッションとは?
グループディスカッションとは、数名で構成されたグループで、決められたテーマの議論を行うことです。議論のテーマやメンバーは当日にわかることが一般的で、時間内に結論を導き出す必要があります。なお、企業によっては発表の時間が設けられることもあります。
グループディスカッションの種類
グループディスカッションは、大きく2つの型に分けられます。1つめは、決められた課題やテーマに対して議論し、解決策を結論とする「課題解決型」です。2つめは、決められた課題やテーマに対して議論し、グループとしての結論を導き出す「自由討論型」です。
企業がグループディスカッションを行う目的
企業がグループディスカッションを行う目的は、面接やエントリーシートなどの書類ではわからない能力や個性を見ることです。グループディスカッションでは、積極的な発言や姿勢、協調性やコミュニケーション能力はあるかなどがチェックされます。
企業が見ている具体的なポイントは後述します。
初めてでもわかる!グループディスカッションの進め方
グループディスカッションの大まかな流れや一般的に行われる内容を解説します。
1.議題や概要の説明
まずは企業担当者が、以下のような項目について説明を行います。聞き逃すと議論がスムーズに進まなくなる恐れがあるため、メモを取っておくとよいでしょう。
- 議題
- グループ構成
- ルール
- 制限時間
- 禁止事項
2.自己紹介と役割決め
グループ内のメンバーについて、お互いを知らないままでは会話がスムーズに進みません。まずは、簡単な自己紹介を行ってから議論における役割を決めます。役割は立候補で決めるのが一般的です。
役割の詳細については後でくわしく説明します。
3.時間配分の決定
司会進行やタイムキーパーが中心となり、企業から与えられた時間を配分していきます。
工程と時間配分の例
1. 議題についてグループで話し合う(5分)
2. 個人の考えをまとめる(5分)
3. グループ内の意見をまとめて結論を出す(15分)
4. 発表の準備をする(5分)
4.テーマのすり合わせや掘り下げ
単純な議題やテーマでも人によって定義が異なるケースがあるため、事前に定義をすり合わせておく必要があります。グループ内の認識のズレを防ぐためには5W1Hを意識し、テーマを掘り下げて全員が共通認識を持てるようにしておくことがポイントです。
5.意見の集約と結論づけ
意見を集約する際は、反対・賛成・別角度の意見などの結論をグルーピングして整理します。結論づけには、最も有力な意見を結論とする、似た意見を掛け合わせる、意見の共通点を結論にするなどの方法があります。全員が納得できる結論を出すために、意見の妥当性を確かめつつ論理的なゴールを見つけましょう。
6.プレゼン・発表
プレゼンや発表を行う際は、議論の過程を知らない人にも、どのような結論に至ったのかをわかりやすく説明できるようにしましょう。発表者の言動はもちろん、見守るメンバーの言動も見られているため気を抜かないことが大切です。
グループディスカッションにおける役割
グループディスカッションをスムーズに進めるための役割について、くわしく紹介します。
司会進行
司会進行は、グループディスカッションの進行役です。個人に意見を求めてまとめたり、議論を結論まで導いたりします。以下のような人におすすめの役割です。
- リーダーシップがある
- 話の要約や整理が得意
- 聞き上手
書記
書記は、パソコンやホワイトボードにわかりやすく議論内容やポイントをまとめます。以下のような人におすすめの役割です。
- 字がきれい
- マルチタスクが得意
- 論理的にまとめられる
タイムキーパー
タイムキーパーは、時間内に議論を行い、結論を導き出せるようにメンバーに声をかけながら時間を配分・管理します。以下のような人におすすめの役割です。
- 冷静に判断できる
- 臨機応変に対応できる
発表者
発表者は、企業の採用担当者やほかのグループの人に向けて意見を発表します。以下のような人におすすめの役割です。
- 議論の展開を正確に把握できる
- 論理的に話せる
- 堂々としている
- 声の大きさや話し方に自信がある
役割なし
グループの人数や状況によっては役割がないケースもあるため、積極的な意見や議論を活性化させるサポート役として活躍しましょう。以下のような人は役割がなくても、実力を発揮できます。
- 意見を出すのが得意
- 発想力に自信がある
- 臨機応変にコミュニケーションが取れる
グループディスカッションで企業が見ているポイント
グループディスカッションを通して企業が見ている評価ポイントには、以下のようなものがあります。
協調性やコミュニケーション能力があるか
グループディスカッションでは、通常の面接ではわかりづらい協調性やコミュニケーション能力がわかります。例えば初対面の人同士でも、意思疎通がスムーズに図れるかというコミュニケーション能力がチェックされます。
また、自分とは違う意見でも受け入れられるか、相手の意見を否定せずに説得できるかなどの協調性もチェックされるので注意しましょう。
論理的思考力があるか
グループディスカッションでは、論理的思考力があるかをチェックするため、問題が複雑に絡み合った議題を出すケースがあります。複雑な問題でも冷静に整理して筋道を立て、解決に導くような心がけが必要です。
グループに価値を提供できるか
個人がグループ内でどのように動き、価値を提供できているかもチェックされます。積極的に参加する、多くの意見を出す、進んで役割に立候補するなど、グループに価値を提供できる行動を心がけましょう。
初めてでも心がけたいグループディスカッションのコツ
グループディスカッションが初めてでも、以下のコツを押さえておくと冷静な行動ができるでしょう。
評価基準を知る
グループディスカッションでは、発表内容よりも結論に至る過程が重視されます。例えば、コンサルティング業界の場合は論理的思考、営業職の場合は積極性やコミュニケーション能力など、業界や職種によって重視されやすいポイントが異なるケースもあります。
グループに貢献できそうな役割を選ぶ
グループディスカッションは役割で評価されるわけではなく、議論に参加する姿勢が重視されます。自分が得意な役割はグループに貢献できるため、自分の適性を知っておくことも大切です。初めて参加する場合は役割なしを選び、協力しながら流れや雰囲気をつかむのも良いでしょう。
メンバー全員で積極的に参加する
グループディスカッションは、役割よりもグループメンバー全員が積極的に参加することが求められます。メンバーと協力し合い、人任せにしないなどグループの一員として責任を持つことが重要です。
時間内にすべてを完了させる
グループディスカッションでは、設定時間内に結論を出すことが重要です。活発に議論を交わし、良い発表になったとしても、時間内に結論を出せない場合は評価しない企業もあるため注意しましょう。
グループディスカッションで評価されやすい行動
グループに貢献できる行動が取れていれば高評価が得られやすいため、以下のような行動を心がけましょう。
- 発言しやすい雰囲気や緊張が和らぐ雰囲気を作る
- 論理的でわかりやすく説明する
- 意見を的確に要約する
- 脱線した議論を修正する
- 人の意見を否定しない
- 話をさえぎらず、人の発言が終わってから意見をいう
- 意見がないときはサポート役に徹する
初めてグループディスカッションに参加する際の注意点
初めてグループディスカッションに参加する際は、以下の注意点を忘れないようにしましょう。
グループに貢献することを忘れない
グループディスカッションでは、いかにグループに貢献できるかが重要です。自分に注目を集めるため、ほかのメンバーを否定したり見栄を張ったりするなどのアピールは禁物です。自分が目立つのではなく、グループに貢献することを忘れないようにしましょう。
固定概念にとらわれない
グループディスカッションの結論は、あらゆるパターンが想定できます。正解にとらわれ過ぎず、どのような意見であっても間違いではないという認識が大切です。また、役割にこだわり過ぎず、与えられた役割に責任感を持ってグループに協力することを意識しましょう。
合わない人の意見も否定しない
グループ内には、自分の意見を押し通して議論を破綻させる人がいるかもしれません。うまく議論が進まず嫌な気持ちになるかもしれませんが、企業側は意見を押し通す難しい人に対し、どのように対応したかをきちんと見ています。感情的になりすぎず、相手の意見もまずは聞き入れてみましょう。その上で意見を交わしたり、チームで多数決を取ってみたり協業しながら議論を進められる方法を見つけていきましょう。
初めてのグループディスカッションへの備え方
初めてのグループディスカッションは緊張するものです。グループディスカッションの模擬面接や対策講座で流れや企業が見るポイントなどを把握するなど、日ごろから準備や練習をしておくと、いざというときも安心感を持って挑めるでしょう。
初めての参加はなかなかうまくいかないこともありますが、2回目、3回目からコツがつかめることもあるため、あまり難しく考えすぎずにまずは経験してみることが重要です。
友達同士の練習や模擬練習を行うキャリアセンター、エージェントなどを活用し、グループディスカッションの練習をして慣れておくのも良いでしょう。
初めてオンラインのグループディスカッションに参加するときに意識したいこと
近年は、オンラインでグループディスカッションを行う企業もあります。オンラインでの参加が初めての場合は、オンラインならではのコツを押さえておきましょう。
オンラインでは、話すタイミングがかぶったりラグが生じたりするため、発言のときは手を挙げるなどのルールをあらかじめ決めておくことがポイントです。挙手機能、拍手や笑顔の絵文字などを使い、発言しやすい雰囲気を作るのも良いでしょう。
ネットワーク環境が悪いと思ったように議論に参加しづらくなるため、事前にネットワーク環境も確認しておくことをオススメします。
また、オンラインは反応が伝わりづらいため、普段より大きめにリアクションを心がけましょう。
ホワイトボードの代わりに図や動画を使う、画面共有をすることなどもあるため、zoomなどの就活でよく使われるWEBシステムの機能に慣れておくこともポイントです。
まとめ
初めてグループディスカッションは、何かと不安になるでしょう。しかし、進め方や企業が見ているポイントがわかっていれば、安心して臨めます。紹介したコツや注意点を繰り返し読んで、ぜひ参考にしてください。
キャリタス就活エージェントは、グループディスカッション講座や面接対策講座など、学生さんのニーズに合わせて年間200回以上のセミナーを開催し、実践的なサポートも得意としています。セミナーやキャリアアドバイザーへの個別相談を活用し、納得いく就活を進めてみませんか?
どんなお悩みでも大丈夫ですので、ぜひお気軽にキャリタス就活エージェントを活用してみてください。